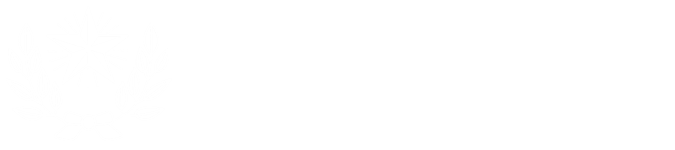保護者会レポート(1/3)
6月21日、保護者会が行われました。
今回の保護者会のテーマは、「ヨハネの学びの根幹をなすパラフレーズとは」。
ヨハネ研究の森における「学び」とは、「研究」とは、という問いの核心に、研究員それぞれの「ことば」と、各グループの研究実践の両輪から迫っていくような場となりました。
その様子を三回に分けてお伝えいたします。
*
「パラフレーズとは何か。」
今回の保護者会は、私にとって今までになく特別な時間となりました。各研究室ごとに、来る日も来る日も対話を重ね、共に手を動かして創り上げてきた研究発表を、日々を共にしていない保護者の方がたに見ていただき、互いに学び合う、大切な時間となりました。
思うようにできなかった、もっと良くできたかもしれない、けれども、今自分たちにできる最高の形で、私達のことばで、研究をお伝えできたという達成感が、どの研究員の心にも溢れていると思うのです。
今回の保護者会では、どの研究室も、どの研究員も、ヨハネで最も重要な研究テーマである「ことば」を見つめ、研究員へのインタビューや、劇作家の井上ひさしさんによるテレビドラマ『國語元年』のパラフレーズを行うという研究実践を通し、それぞれの方法で「パラフレーズとは何か」を表現していきました。
ヨハネでは、汽水でも淡水でもなく、陸でも海でもないゆらぎの中で、豊かな生態系が形成される干潟の環境になぞらえ、多様な研究員が、ことばを重ねて、共に一つの場を創っていくことを「干潟づくり」と呼び、大切にしています。私は保護者会の中で、ああ、これが「干潟」なのだ、と実感しました。
「パラフレーズとは何か」。そこに正解はありません。
保護者会の中で出てきたどのヨハネ生も、一人として、全く同じ説明の仕方をしていた人はいませんでした。人によって着眼点は異なりますし、使う言葉も違います。パラフレーズの実践を見ても、小説風だったり、絵本風だったり、はたまた、舞台を日本からイギリスに変えて英語版を作成したり、物語のプロットや背景の概要を俯瞰的に説明したりと、研究室ごとの違いが色濃く、彩り豊かに表れていました。
ヨハネの学びは、あらかじめ正答が決められたテストで、教科書に書かれたままに暗記した単語や公式などを正確に記入するような「勉強」のあり方とは180°違います。事前に貼り付けるようにして、誰かの書いた文章を丸暗記しているのではなく、各自が「パラフレーズとは何か」、自分たち自身で咀嚼し、ことばにしているのです。
だからこそ、「このようにも考えられる」「こんな意味があったのか」という気付きがあります。そして、「パラフレーズとは何なのか」という形が、より鮮やかに、角度を変えて、広く、深く見えるようになりました。
「ことば」はヨハネ生にとって、永遠のテーマです。では、「ことば」によって切り開き、「ことば」にすることを通して積み重ねていくヨハネの日々の学びが、この先どのようにつながっていくのか。それは、保護者会に帰ってきてくださり、司会として全体を構成してくださった卒業生の背中に、教えていただいた気がしました。誰のことばも即座にパラフレーズし、楽しく、知的に、聞き手に分かりやすく、広げたり、繋げたりしながら、自在に思考していく、「ことば」の熟達者としての姿を見ました。
思考の淵源であり、見える世界を切り拓き、生き方を変えていく「ことば」を組みかえていきます。「ことば」が道を形づくっていき、未来につながっていく確信を、強く抱いた一日でした。
この豊かな干潟の中で話されていた誰の「ことば」も、余すことなく、自分たちの糧にしてまいりたいです。